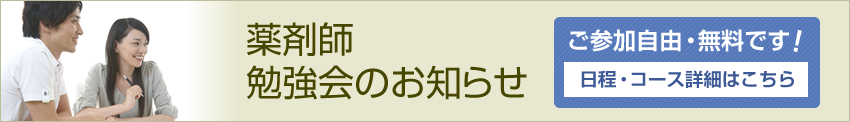半年前に<骨の薬が骨壊死の原因?>というタイトルで顎骨壊死のことを書きました。
あのころはそんなに騒がれていなかったのですが、歯科医師会が色々動き出しました。
最近歯医者さんに行った方は見覚えあると思いますが、
目立つ所、たとえば会計の横や座ると嫌でも視界に入る壁に、
「骨粗しょう症のお薬を服用されている患者様へ」と歯科医師会からの顎骨壊死に関するポスターが貼っています。
BP製剤と額骨壊死に関する新聞報道もありました。
このことで薬局でも様々な質問を受けます。
「辞めなあかんて書いてた。いつから辞めたらいいの?」
「新聞で見たけど、怖いから先生に薬変えてもらった」→エビスタに変更
「この薬きついってこと??」
「歯医者さんが3年飲んでたら、抗生物質効かない体になるって・・・怖いやん」
・・・・最後のコメントは骨が壊死すると言いにくいから話変えた?
いくらなんでもその変え方はないでしょう、といいたいですが。
代表的なボナロンの帝人ファーマのMRさんが詳しく勉強会してくれました。
原因と推測されることやリスク因子は前のブログと同じです。
データーを色々教えていただいたので、ちょっとご紹介。
2004年~2005年の豪州調査によると
骨粗しょう症・骨Pajet病・悪性腫瘍の3疾患のBP系薬剤投与例全体(経口・注射)の顎骨壊死の発生率は0.05~0.1%、その内骨粗鬆症の発現率は0・01~0・04と低く悪性腫瘍が0.88~1.15と上がりました。
さて、これが「BP系薬剤投与中の抜歯施行例」とリスク追加になると発現率は7.5~9倍と高値になります。リスク因子の中でも抜歯がかなりの高リスクであるということですね。
外来での処方頻度が高い経口剤のデータとしては、
米国口腔外科学会ではアレンドロネート(ボナロン・フォサマック)の製造社のデータから、報告頻度は「10万人年あたり0.7件」
欧州骨粗鬆症WGでは各製薬企業に送られている自発報告の件数から「10万人年あたり1件未満」と算定されています。
経口では確かに低頻度ですが、確固たる原因がわからないまま何故早くに歯科医師会が注意喚起をするのかと言うと、「顎骨壊死」というのは歯科分野では最終的には掻爬して骨移植、という重篤な疾患であるということがあげられます。
そのうえ米国口腔外科学会が顎骨壊死とBP製剤の管理戦略のガイドラインを出しているので、それをもとに具体的な注意喚起ということです。実際米国が早々とガイドラインを作ったのは、はっきりと原因やリスク回避が解明された訳ではないのですが、なにせ「訴訟大国」、その防御策としてガイドラインが早くに作られた一説もあります。日本ではこの夏あたりに口腔外科学会からガイドラインがでるのでは、とのことです。
以下、米国口腔外科学会での経口BP剤投与中に抜歯等の浸襲的歯科処置が必要のなった場合のBP系薬剤の投与に関する文章です。
「経口BP製剤による顎骨壊死発生のリスクは非常に低いものの、経口BP製剤による治療期間が3年を超えると上昇する。ただし、コルチコステロイドを長期併用している場合には、経口BP製剤による治療期間が3年未満でも発生リスクは上昇すると考えられる」
① 経口BP投与期間3年未満でコルチコステロイド併用、あるいは経口BP投与期間が3年以上の場合は、
患者の全身状態からBP製剤を中止しても差し支えないのであれば、歯科処置前の少なくとも3ヶ月間はBP製剤の投与を中止し、骨治癒するまでは再開すべきでない。
② 経口BP投与期間3年未満で危険因子が無い場合は予定された浸襲的な歯科処置の延期・中止や経口BP製剤の投与中止の必要は無い。
※ 危険因子・・・・コルチコステロイド療法・糖尿病・喫煙・飲酒・口腔衛生の不良・化学療法薬
この「3ヶ月の休薬」というのも、今のところ理論も根拠もないそうです。
・・・・・一番大事なこと、「虫歯は3ヶ月待ってくれない!!」