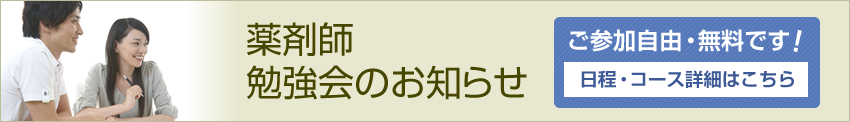昨年度から新聞紙上で「後期高齢者医療」の負担の延期が何ヶ月とか、首相が変わったとたんに凍結やら、なんだかごちゃごちゃしていて「だから結局どうなのよ??」と言っている間に年も明け、4月の制度始動にむけ各自治体の詳細が明らかになってきました。
特に関西地方の調剤薬局などでは
「保険料払わなあかんようになって、えらいこっちゃ、どないなってるんかいな、
ほんまにもう~たまらんわ」
・・・・と高齢者の愚痴を聞かされるケースが多発することを踏まえ(笑)
制度の基本をおさえておきましょう。
皆様ご存知の通り、本年度4月より後期高齢者医療制度が始まります。
75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上になるとこれまでどんな保険に入っていた人もすべてこの「後期高齢者医療」の保険に新しく加入することになります。
当然、息子さんの保険にご家族として入っていて今まで全く保険料を負担していなかった方も75歳のお誕生日のケーキ(饅頭?)とともに「保険料」が発生するわけです。
しくみは都道府県ごとに全市町村が加入して設置される「後期高齢者医療広域連合」が運営しますが、介護保険と同じく都道府県によって「保険料」に格差がでてきます。
産経新聞の調査によると
厚生年金のみを受給する単身者の場合(年額208万)だと、一番高い福岡県が年額保険料10万1750円で1番低い長野県が7万1700円とこれほどの地域格差があります。
これは比較しやすいように所得格差を除いて計算しましたが、厚労省の発表による所得も含めた計算では1番高いのは神奈川県で1番低い青森県の約2倍の平均保険料がはじきだされました。
さて「保険料」ですが被保険者全員に等しく課せられる「均等割額」と所得に応じて課せられる「所得割額」の合計額になります。
具体的に大阪府についていいますと、「被保険者均等割額」は年額4万7415円。この均等割には基本的には軽減措置があり、たとえば基礎控除額を超えない世帯で7割軽減その他5割3割軽減とか。
これに「所得割額」をたして合計を出します。
とは言ってもピンとこない「だから結局いくら払うの?」と言うことで、モデルケースを見てみましょう。
(大阪府の場合)
<単身世帯、年金収入120万のみ>→1万4224円
<同、180万>→6万1368円
<同、240万>→12万2931円
<75歳以上夫婦2人世帯、夫年金120万、妻50万>→2万8448円(夫婦の保険料合算)
<同、夫180万、妻50万>→7万850円
<同、夫240万、妻50万>→17万346円
こんな感じです。(すべて年額)
但しこれまで社会保険のご家族で保険料を負担されていなかった人には急に発生する保険料の激変緩和の観点から2年間は所得割額は課せられず、均等割額も5割軽減されます。
そして時期的な特例ですが平成20年の4~9月までは均等割額がなし(つまり保険料ゼロ)10月~平成21年の3月間では均等割額が9割軽減と措置があります。しかしこれらの措置はあくまでも社会保険の家族で負担ゼロの人に対してだけです。保険料を払ってきた国民保険の人や社会保険の本人は最初に書きました年収による軽減措置になります。
ついでに前期高齢者医療(70歳~74歳)の窓口負担がこの4月から2割になることが法改正で決まっていますが、こちらも国の措置で平成21年3月までは1割負担に据え置かれることになりました。
色々述べましたが結局「減額措置」というものはある一定期間だけで負担増は間違いなしです。
というか、措置期間が切れるころにはまた財政難で変更があるかもしれませんしね。
保険料は「使った医療費」から皆の料金アップにつながるので、なんといっても医療費を削減しないことには「台所は火の車」状態なのは間違いないです。
ジェネリックやセルフメディケーション、「未病」という言葉もあります。薬剤師として経済も考えてみませんか?