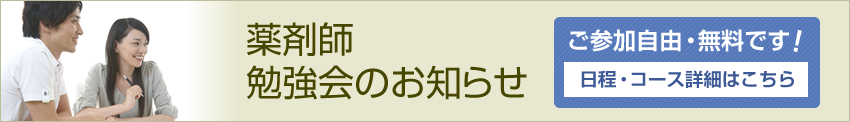10月29日の産経新聞に「川崎病、2年連続1万人突破」と記事がありました。
昭和42年に当時日赤の川崎富作先生が「急性熱性皮膚粘膜淋巴線症候群」として報告されたのが始めてです。世界でも「Kawasaki Disease(KD)」 と呼ばれています。
冠動脈を含む全身の血管炎症候群で、炎症が続いた後に冠動脈障害を10~15%に合併します。
日本や米国においては小児における後天的な心疾患の第一の原因になっています。
発表されたのは40年も前ですが、原因はウイルス感染説もありますが未だ確定はできず、不明です。
全国調査は昭和45年から行われていますが、過去に昭和54・57・61年に大流行がありました。(流行って事はやはり感染なのでしょうか?)
患者数が1万人を突破したのは57・61年だけだったのに、最近は右肩上がりに増加し、平成17年・18年と1万人越えです。また、0~4歳の罹患率も特にこの10年間程急増です(少子化なのに・・・・)
主な発病時の特徴は
発熱・両目の充血(目やにはなし)・イチゴ舌・首のリンパ節の腫れ・四肢の硬性浮腫
後に皮膚がボロっとめくれる・大小さまざまな形の発疹など。
とくに発疹ですが、BCGの接種部位が赤くなることが多いですが、これは他の疾患にはない特徴的な現象です。心臓後遺症がなければ1ヶ月ほどで炎症は治まり、リウマチのように慢性化しませんが念のため定期的な検診が必要となります。
冠動脈瘤が残っても小さなものだと治療で消えてしまうのですが、大きなものだと狭窄性病変に進行する場合もあります。性差は1.3~1.5:1で男児に多く、年齢分布は4歳以下が80~85%です。
しかしながら、疾患発表時とは違い治療法の確立で死亡率は劇的に低下し、かつて2%を超えていた致死率は0.01%まで下がりました。以下「川崎病急性期ガイドライン・日本小児循環器学会」からの抜粋です。
現時点で最も信頼できる抗炎症療法は、早期に大量(高用量)のグロブリンの点滴静注療法 (IVIG療法)。なかでも2g/kg/日の超大量単回投与や重症度に応じて1g/kg/日を1日又は 2日連続投与がより効果的といわれている。
原則としてIVIG療法と抗血小板療法を併用する。急性期は腸管からの吸収が悪く血中濃度 の上昇が悪いので急性期は中等量のアスピリン(30~50㎎/kg/日)、解熱後は3~5mg/kg/日の投与。冠動脈に障害が残さない場合も血小板凝集能は数ヶ月間 亢進してお り、炎症の程度が陰性化した後2~3ヶ月間は継続されるのが望ましい。
バイアスピリンもバファリン81も適応ありますね。
子供に関わる病気なので、できれば避けたいけれど原因がわからない現在では防ぎようがありません。しかし、合併症を最小限に防ぐ事はできます。
とくに冠動脈拡張病変は第9病日あたりに始まるといわれているので、前述のような特徴に早く気づき、1日でも早く(できれば第7病日以前)にIVIG療法を行うことが合併症を防ぐ為にとても有用な事です。