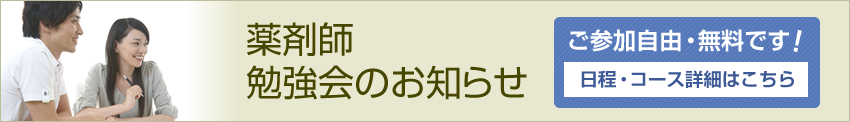境界性人格障害(以下BPDと表記)、いわゆる「ボーダー」といわれる人々です。人格障害という言葉が誤解と偏見をまねくので、最近では「境界性パーソナリティ障害」といわれています。
境界性とは、もともと神経症と精神障害(主に統合失調症)との境のことでしたが、最近では鬱などの気分障害とのかかわりなどもあり、現在は米国精神医学会のマニュアル<DSM-Ⅳ>では10ある人格障害の1つに分類されます。
本人や家族には「人格障害」という言葉にショックを受ける場合があるので、
診断名をはっきり告知していない場合も多いです。
ではどのように判断するの?と言うと、<DSM―Ⅳ>によると、
以下の9項目のうち「5つ以上」で示されます。
1.見捨てられ不安
2.理想化とこき下ろしに特徴づけられる不安定な対人関係
3.同一性の障害
4.衝動性
5.自殺企図
6.感情不安定
7.慢性的な空虚感
8.怒りの制御の困難
9.一過性の妄想様観念/解離
具体的行動では、たとえば他人を過大に評価し理想化したと思えば、
その人が自分の意にそぐわないと異常に激しい攻撃性を出します。
そこで精神科・心療内科で治療しにくい理由のひとつに、自分の思うような治療や返事が返ってこない場合「信頼している先生が裏切った、ここはヤブ医者だ!他の病院にかえよう」と、理想化からこき下ろしに急激に気持ちが変化し、ドクターショッピングをする人が多いのです。
なんだかこのように聞いていると、わがままの極みのように聞こえますが、病的に反応してしまいうと言うことです。ですから余計に健常者(単なる性格的なもの)との区別に診断が慎重になります。
前述の<DSM-Ⅳ>以外にも、世界保健機関国際疾病分類<ICD-10>での診断や、場合によっては心理テストなども行い数回の面談で判断します。
原因は?となると、色々な説があり確定していません。
やはり脳内の伝達物資の異常、大脳海馬の萎縮、幼少期の強度のストレスによるもの、等。
治療は、薬物療法と共に認知療法・家族療法などの心理的治療、精神分析による自我の再構築など、種々の治療を組み合わせます。
使用薬ですが、うつ病のように治療指針がしっかりしているわけでもなく、色々調べますと個々のドクターによって様々な見解があります。
SSRI・SNRI・非定型・抗不安薬・気分調製薬など、最近の学会誌ではMARTA(クエチアピン・オランザピン)が著効する例が紹介されています。
もともとリストカットなど自殺企図があるので、三環系抗うつ剤やリチウム、バルビツール酸系睡眠薬等は
大量服薬の可能性があるので、慎重な投与が必要です。
ベンゾジアゼピン系抗不安薬も不安・イライラを鎮める為に処方されますが、BPDの人には焦燥感や衝動性を増してしまい、自傷行為や他傷行為の衝動にかられてしまうという見解もあります。
うつ状態になるときもあるので、本人が「うつ病」と思い込むケースも少なくありません。
決定的に「うつ病」または「躁うつ病」と違うのが、気分の波が、数時間から数日で極端に変化するところです。人生観や価値観まで両極端にかわってしまう場合もあります。
「うつ病と思い込んで来たBPDの患者さんにはどのような処方をするのですか?」と
直接精神科Drに質問したら「・・・・何出すと思う?」と逆質問され「???」
「それはね、少量のスルピリドだよ、攻撃性も抑え鬱症状にもきくしね」と。
また、ある自宅開業している心理カウンセラーに
「BPDの人がカウンセリングに来て攻撃性が増し危険な状態になったことないのですか?」と聞くと
「BPDの人はね、いわゆるボーダーラインを超えないと普通の人なのよ、
ボーダーラインを超えない接し方をすれば攻撃性はでないし本人も楽なのよ」と
教えていただきました。
結局、衝動性をコントロールする治療がBPDの人や支えるご家族にとって、有効なのだと感じています。脳内伝質等がより深く解明されると、数年後には色々治療法が確立されるかもしれませんね。