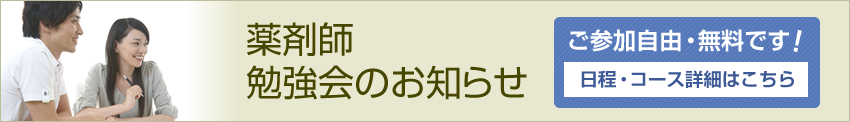最近、健康保険で漢方薬がよく処方されるようになりましたね。
なかなか馴染みがないと服薬指導しにくい分野です。
大学時代生薬ゼミでして、教授がアフリカから取ってきた天然木を、せっせかせっせか
成分抽出していました。
最後にナントカナントカ強心配糖体がでましたが、何だったか記憶の片隅でゴザイマス・・・・・。
てな事もあり、漢方薬店にも勤めていた経験からのお話。
まあ凄い数のエキス剤だし、葛根湯という処方に対して、感冒・肩こり・じんましんと
全く違う適応だし。
しかも中身の生薬の種類は・・・・・ん~!覚えきれない!
では、服薬指導のポイント。
処方箋で出された場合は、処方決定はDrにあるわけなので、実証・虚証・陽・陰etcは
とりあえず、ちょっとおいといて。
漢方はいくつかの生薬から構成され、合剤として力を発揮するわけですが、
それぞれ生薬単味の基本的な作用があります(単品で昔から薬用酒としても使ってますよね)
この構成生薬に注目し、単品の特徴や主な作用を覚えることで、
効果や副作用など服薬指導時に注意しなければならない事がわかりやすくなります。
たとえば作用面でこれらの生薬が入っていると、
葛根→発汗作用→風邪に。
竜骨・牡蛎→カルシウム→イライラに。
茯苓・朮→利水作用→浮腫に。
当帰・川キュウ→ふる血をとる→婦人病に。
人参・大棗→滋養強壮→体力低下に。
桂枝→体を暖める→冷えてる人に。
となります。
たとえば「五苓散」。
利水作用があるということは、浮腫にも使いますが、
胃に対しては胃に余計な水分があると、胃もたれの原因になったりします。
だから浮腫にも使用しますが、悪心嘔吐にも使うという訳です。
最近泌尿器科からEDで桂枝加竜骨牡蛎湯がよく処方されますが、
桂皮で下半身暖め、大棗で体力回復し、竜骨・牡蛎で精神安定し・・・・・と考えると
なるほど!と思うのです。