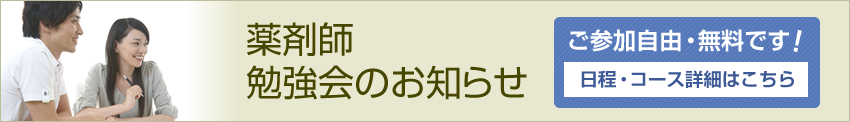「掌蹠膿庖症」
この病名が一般にも知れ渡ったのは女優の奈美悦子さんがTVで闘病を語ってからです。
これと同時にその治療に使った「ビオチン」が有名になりました。
ビオチンとは水溶性ビタミンで以前はビタミンHと呼ばれていました。
「H」はドイツ語で皮膚を意味する「Haut」の頭文字で、もともとは皮膚炎を治すビタミンとして発見されたものでした。ずっとビタミンHと思っていたら、知らない間に現在はビタミンB群(B7)に分類されていました。
ビオチンは腸内細菌によって作られますが、レバー・魚介類・卵黄・豆腐等多くの食品にも含まれています。食品中のビオチンは蛋白質と結合した状態でビオチニダーゼという酵素によって結合が切り離されて遊離型になってから初めて腸から吸収されるそうです。
普通の食生活ではビオチン不足になることはありませんが、長期間の下痢や抗生物質の服用で腸のバランスが崩れている場合やビオチニダーゼの活性が異常に低下している場合や、卵白(生)に含まれているアビジンはビオチンと強力に結合し吸収を阻害しますので、大量の生卵白の摂取が続くとビオチン欠乏になります。
欠乏するとエネルギー代謝、免疫機能、コラーゲンの合成等の低下が起こり、アトピー性皮膚炎や乾癬、脱毛症、掌蹠膿庖症などの皮膚疾患や糖尿病、易疲労感など色々な症状が起こりやすくなるといわれています。
ビオチン散は医療用では扶桑薬品の「フソー」と東洋製化の「ホエイ」があり、ともに0.2%です。
一部では皮膚疾患に対して、このビオチン散を常用量より多い量とビタミンCと整腸剤を同時服用する治療をしている所もありますが、このビオチン大量療法に関しては肯定的なDrと否定的なDrがいらっしゃるみたいで、色々なところで論争があるみたいです。
専門的にはどれほど確立された治療法なのかはわからないのが現状ですが、ビオチン散は常用量でも色々な皮膚疾患に用いられていますので、ビオチン散0.2%「フソー」のほうから添付文書の抜粋を掲載しておきます。
効能・効果 → 急・慢性湿疹、小児湿疹、接触皮膚炎、脂漏性湿疹、尋常性ざ瘡
用法・用量 → ビオチンとして1日0.5~2mgを1日1~3回に分割、適宜増減